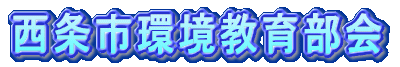
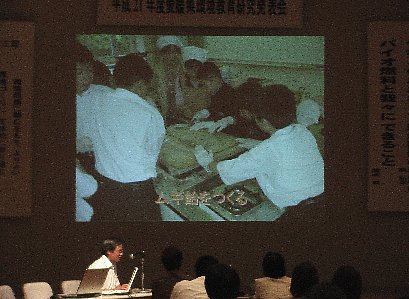
|
・どの学校も体験活動を大切にしていた。活動を通して児童の意識の変容も見られた。 ・各校の取組をきちんと把握して発表されていることから、支部の協力体制がしっかりしていることが感じ取れた。 ・環境教育は短期間で成果が得られるものではない。担当者だけでなく、学校全体で長期的な見通しを持ち、体制を整えなければ難しいと感じた。 ・小松中学校の秋山先生の実践発表は、アイディア豊かで児童生徒が楽しめる活動であると思った。地域力を感じた。 ・どの取組にも地域の方の協力と教師の熱い指導力が必要だと感じた。 ・豆腐作りは、小学校の児童でも楽しく活動できた。おからを使ったドーナツ作りなど、体験活動をいろいろと取り入れて実践していきたい。 ・地域の特性を生かした取組が参考になった。 ・給食の残菜に目を向けてみたい。 ・具体的な実践が写真などを使って分かりやすく紹介されていた。 ・児童に、その活動が環境にとってどんなよい効果があるのかを、きちんと理解させて取り組ませているのがいいと思った。 ・パンの再利用がおもしろいと思った。続くとさらによかった。 ・身近なことから実践していくことが大切だと思った。 ・廃油石鹸作りは、地域の方を講師に迎え、環境教育の素晴らしい取組ができていると感じた。毎年続けることで、買ってくれる人も、また、エコ活動に協力していることになる。安全に気をつけて続けてほしい。 ・エネルギーの循環にたいへん興味がある。学校でどのような活動につなげていくのかのヒントを得られた。本校でもチャレンジしていきたい。 ・環境マイスターとの連携に興味をひかれた。 ・それぞれの学校での取組を聞いて、どんなことでもできることから取り組んでいけばいいんだと思った。 ・ゴミは資源として見る目を育てていくことが、リサイクルにつながると思った。 ・市全体の取組の方向性が分かり参考になった。 ・無理のない取組や、継続することの大切さを感じた。 ・給食の生ゴミを堆肥にする活動は、地域にも広げていくべきだと思った。 ・環境マイスターとの連絡方法が知りたい。 ・橘小のグループ別課題追及5つのカードを詳しく知りたい。 ・南中の実践はとにかくやってみたことが素晴らしい。効用についても調査してほしい。 ・循環型社会は、社会の組織が整備されていなければ機能しない。環境コーディネーターの位置づけなど、今後考えていかなければならない。 |


