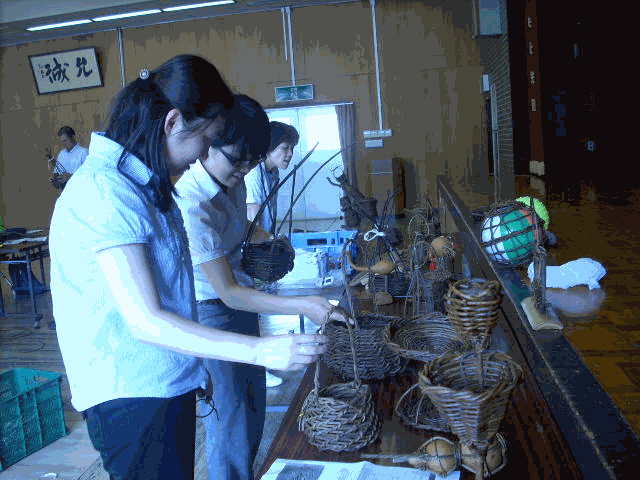1 会場 八幡浜市中央公民館保内別館 2階大会議室
2 講師 松田 亀久雄 氏 (松田酒造株式会社代表取締役) かずら細工指導者
3 実習(かずらの小篭作り)
(1)松田氏よりつづらかずらや篭の基本的な作り方の説明を聞く。
つづらかずらは四国に多く生息し、特に北側の斜面にあるそうである。他のかずらとの見分け方は、かずらの切り口が菊の模様になっていることである。かずらは、11月から12月頃に採取し、5分ほど熱湯で煮て(熱湯に漬けておいても良い。)よく乾かして保存しておく。篭などを作るときは、かずらを一昼夜水に漬けて柔らかくしてから使う。
篭は、たて芯用に少し太めのものを選び、70cmの長さのものを4本用意し、2本と2本を十字に重ね、少し細めのものを選んで1本のかずらで、たて芯の上を山、たて芯の下を谷として3周回していく。その後、1本ずつに分け、1山1谷と2回ほど編んでいき、最後のたて芯を1本切る。たて芯が奇数になったところで、編んでいく。途中で継ぎ足す方法や持ち手の作り方、篭の上の縁の始末の仕方なども教わり作成に入った。
(2)つづらかずらの篭作りに取りかかる。
ほとんどの方が初めての挑戦であったが、作り方が分かるとどんどんと進めていき、楽しく製作することができた。和やかな雰囲気の中、良い編み方を参考にして自分の作品に取り入れたり、できた作品を鑑賞し合ったりしながら、活動に取り組んだ。