○ はじめに
私は、先生というよりは、フィールドワーカーとして活動しています。先生方より、たくさん歩いていると思います。お配りしたポスター「佐田岬半島SОS図鑑」は一枚ものの図鑑です。本のタイプの図鑑では、本棚にしまわれてしまうので、気軽にいつでも見てもらえるように作りました。カワウソをはじめとした環境省のレッドデータブックに載っている動植物の写真を載せていますが、「ナメクジ」のようにどこにでもいそうな生物でも、みなさんが目にするのはほとんどが「コウラナメクジ」という外来種です。今日は、佐田岬半島の自然を紹介しつつ、エネルギー問題を野生生物の側から見るとどうなるのかということ伝えたいと思います。自然界の声なき声を代弁していると思って聞いてください
「身近な自然に(・)学ぼう」というタイトルですが、今まで私たちが習ってきたものは、「身近な自然を(・)学ぼう」だったと思います。霊長人間の英知で、生物の解剖をしたり、ホタルなどの野生生物の飼育をしたりというのは、かなり上からの目線で自然を捉えていると思います。わたしが主宰している「どんぐり自然楽校」は、字の通り自然に親しんで楽しんで、自然から学ぼうというスタンスでエコアクションを展開しています。今日は、自然こそが私たちの師匠だということを伝えたいと思います。
○ 佐田岬半島の紹介
日本一細長い佐田岬半島は、四国の最西端で、全長約50kmです。近くにある出石山までを生態系のひとまとまりとしてとらえています。この半島は、四国唯一2つの海をもっています。北側には玄海灘からの寒風が吹きつける冷涼な気候の瀬戸内海国立公園があり、南側には黒潮からの暖かい海流が当たる佐田岬半島宇和海県立自然公園と呼ばれる一帯があります。一つの尾根をはさんで2つの異なる環境があります。半島が北東から南西に延び、そこへ斜めに風が吹き付けるので、多様な気候現象が生まれます。たとえば、北側では、大野ヶ原でしか見ることのできない種類の植物が佐田岬灯台の近くで見ることができ、南側では、生育北限種の天然記念物もたくさんあります。鳥類で見ますと、佐田岬半島は、国際的な渡りの回廊と言われています。向かいの九州までの距離は、わずか13kmで、渡り鳥にとっては、最短コースを最少のエネルギーで渡ることができるルートです。猛禽類のハチクマなど大きな鳥だけでなく、ヒヨドリやカワセミなどの小さな鳥までいろいろな種類を見ることができます。また、アサギマダラや、ウスバキトンボなどのいろいろな昆虫も渡っています。
この自然豊かな佐田岬半島は、近代資本主義と現代科学の実験場といわれています。伊方原子力発電所をはじめ、58基もの発電風車が稼働しています。また、メガソーラー建設の計画もあります。しかし、そういったものの建設のために、植物の伐採が行われ、土壌もはぎとられしまい、動植物が追いやられたり、希少な植物が失われたりしてしまいます。もし、ソーラーパネルを取り付けるなら、高速道路などのコンクリート法面にすれば、植物を伐採しなくてよいし、景観も保たれるのでないでしょうか。自然とバッティングするのではなく、何とか共生して、持続可能なものにしていければと思っています。根本的には、自然に優しい人工物というものは、一切ないと思います。原子力発電所は、建てられてから30年以上経過しています。もし、事故があれば、この辺り一帯すべてが大変なことになります。またそれに代わる発電風車は、以前には熱帯雨林を伐採していた、大手ゼネコンがつくったものです。風車に落雷があったり、風が強すぎて風車を止めなくてはならなくなったりといろいろな問題が起こっています。停止しているときにも、低周波音が出るので、近隣の住民から苦情も出て、裁判になっているところもあります。もっと怖いのは、一基建てるごとに、その場所だけでなく、周りの道路建設などで多くの木々が伐採されることです。そして、外来種の植物を植えてしまうので、在来種がどんどん少なくなってしまいます。
このあたりは、月の半分は深い霧によって視界が悪くなることが多く、渡り鳥が誤って風車に飛び込んでしまうケースがよくあります。最近では、この場所が危険と学習した渡り鳥たちは、ルートを変えて渡っているようで、以前の10分の1ほどに渡り鳥の数が減少しています。このことが野鳥の繁殖状況影響を与えるのではないかと懸念しています。
○ 高茂草原(こうもそうげん)・小島草原の自然
旧瀬戸町になる高茂草原は、ススキやチガヤが生い茂る原生草原です。ここには、帰化植物はあまりありません。ここでは、高茂牛が育てられていて、たくさんの牛が斜面の草を食べています。人間が草を刈らなくても、「舌草刈り」で牛が草を食べてきれいにしています。この草原の中でも、最も自然度が高い小島原生草原では、カセンソウや、フナバラソウ、スズサイコ、ツチグリなどのレッドデータブックに載っているような希少な植物が生育しています。オミナエシやオキナグサは、人が掘って持って行ってしまったために激減していますが、こぼれた種が、いつか芽を出し、復活することを期待しています。植物がなくなることは、その植物を食べている生物が生きていけなくなるということです。たとえば、ウラギンスジヒョウモンという蝶は、カセンソウの蜜を吸います。また、幼虫は、ニオイタチツボスミレというスミレの仲間を食べます。この3つの種類がうまくかかわりあって生息できているのです。この小島草原では、他にもいろいろな植物と生物との不思議なかかわり合いが見られます。生涯学習事業として行っている「さんきら自然講座」では、必ずこの草原に行って、自然の素晴らしさを感じてもらっています。昆虫なども網で捕まえて見るのではなく、生態をそのまま見て、命を感じてほしいと思っています。他にも夜の星空も素晴らしいので、天の川も見ることができます。ぜひ、夜は電気を消して、外に出てほしいと思います。そうすると節電になるし、夜行性生物を助けることにもなります。
○ これからのエネルギーについて
我々の生活に必要な電力を得るためには、水力発電にしても、太陽光発電、風力発電にしても、野生生物にとっては何らかの影響があります。しかし、発電施設が小規模になればなるほど影響は少なくなります。大規模で集中して発電するのではなく、小規模・分散化して送電線のない社会にしていくことが大切だと思います。地域の企業や電気店、私たち自身が管理・運営していけるシステムにすることで、エネルギーの地産地消化を進め、各家庭で節電を進めていくことだと思います。
○ これからの人材を育てることについて
私の故郷の日土小学校の横には、喜木川があります。この川で、子どもたちが伸び伸びと自然と触れ合って遊べるようにしていきたい、それこそがカワウソの住める環境の復活につながると考え、「カワウソ復活プロジェクト」を推進しています。また、保内町の言葉で、「サンキラっ子」という言葉があります。サンキラとは、とげのあるつる性の植物のことで、転じて一筋縄ではいかない、おてんば娘、腕白小僧という意味として使われています。「子どもは風の子、自然の子」です。不自然な生き方をしていることが多い私たち大人は、子どもたちの生き方に見習わなくてはいけないと思います。大人が子どもに知識を教えるのではなく、私たちが忘れてかけていることを子どもたちの感性や喜怒哀楽から学ぶべきです。
毎月第4日曜日に行われている八幡浜市の諏訪崎自然観察会は、今年で14年目を迎えました。モットーは、「地球の仲間たちの<命>を感じよう」です。生き物の種類を細分化し、名前を覚えるのではなく、植物にも、昆虫にも私達にも共通するもの、「命」を感じようということです。皆さんもぜひ、自然を「観察」して楽しみ、そして、「感察」して命を感じ、大切さが分かったら「看察」して守っていくという、自然観察の三段活用をしてほしいと思います。決して自然「監察」にしてはいけません。
「渚の海援隊」という海での活動もしています。二つの海に囲まれたこの場所は、海の漂着物もたくさんあります。海辺の生き物を観察し、いろいろな漂着物をあつめてアートにしています。なぜこの漂着物がここへ来たのか、そして、これらが生き物にとってどのような影響を与えているかを知るのです。すると、子どもたちはただごみを拾うということから、「大好きなウミガメのためにごみを拾う」ということになっていきます。海の生き物たちへの恩返しをしようという気持ちで一生懸命活動しています。
こういった野外活動だけではなく、「自然界に学ぼうやナイト」という自然環境講座も開いています。毎週第2水曜日に、八幡浜市中央公民館で行っています。内容は、スライド上映会や研究発表です。また、伊方町郷土館では、「佐田岬みつけ隊」という講座も開いていますので、ぜひ参加してください。
伊方町の亀ヶ池湿地のところが開発されるようになった時、近くの小学校の皆さんと協力して在来植物の保護を行いました。現在では、園芸植物を植えずに元の植物だけの素晴らしいビオトープができ上っています。温泉に来られたら、ぜひ立ち寄ってみてください。
○ 終わりに
「自然は在るがままでパーフェクト」です。自然を大好きだという人は大勢いると思いますが、自然から好かれているでしょうか。子どもたちには、大いに自然の中に溶け込み、親しみ、そして自然の方から愛される人になってほしいと思います。そのために、私たち大人も、自然に親しみつつ自分たちのライフスタイルを変えていくことが大切だと思います。
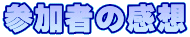 (講話を聞いて)
(講話を聞いて)
・とても感動しました。頭でっかちであったと改めて感じました。子どもたちともっとフィールドに出て行きたいです。
・貴重な動植物の写真を見ることができて楽しかったです。自然を守っていくことが大切だと感じました。
・自然に愛されるという考え方がこれから私たちにさらに必要とされる考え方だと思った。とても勉強になりました。
・自然から愛される人に自分もなりたいと思いました。環境への考え方がよく分かりました。
・大変すばらしかったです。今後も楽しみになりました。
・「自然に愛される人へ」という考え方はとても大切だと感じた。とても有意義な講話でした。
・自然について、知らないこと、気づいてないことが多いことに心が痛くなりました。美しい映像にも心を打たれましたが、自然の美しさにもっと目を向け、守っていけたらと思います。
・家の近くにもタンポポを調査する方が来て、新種のオオズタンポポだと教えてくれました。アカショウビンも毎朝鳴き声が聞こえていました。そのような環境が当たり前だと思っていましたが、そのような自然の大切さを改めて感じました。
・子どもたちが自然に対して何を感じるべきなのか、自然に愛される人へという言葉に感動した。この言葉の意味を生徒にも伝えたい。
・とても分かりやすい講義でした。生き物(人間以外)の視点に立っての人工物に対することを言ってくれたので、自分はやはり「上から」なんだなと実感しました。私は東予に住んでいますが、南予を含む愛媛の自然を大切にしようという気持ちになりました。自然から好かれる人になりたいです。
・「自然に愛される」とはとても難しいことに感じるが、やはりこれからの環境教育を考える上では大切なキーワードであると思う。人間のエゴにならないように気をつけたいと思う。
・「生き物の目線で」というお話に引き込まれました。
・水本さんのスタンスがよく分かった。エネルギー問題もいろいろ勉強になった。自然に感謝です。
・普段の生活では気づかない身の回りの豊かな自然を気づかせていただいた。
・自然に親しむというのは虫を捕まえたり、花を採ったりすることではなく、自然の中で命を感じることだなと思った。人間たちの便利さを求める行動によって自然を壊している事実、ずっと先のことを考えると恐いなと思った。
・どんさんの講演はいつ聞いてもすばらしいと思います。自然から愛される人になりたいです。上から目線はやめたいと思います。
・「自然に愛される子ども」をぜひ育てていきたいと強く感じた。
・環境に目を向けるためには自然体験を通して学ぶことが大切であると感じました。
・初めてお話を伺いました。写真が美しく、お話が興味深く、1時間があっという間でした。子どもたちが先生と野山や草原を歩いたら、環境に対する意識を高めるための種をいっぱいに心にまいてもらえるんでしょう。今日はありがとうございました。
・自然への深いまなざし、ただ自然を守るということではなく、共に在るというような視点を学ばせていただいた。



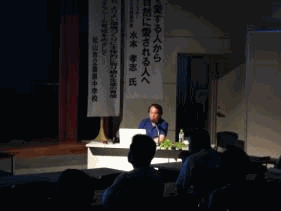
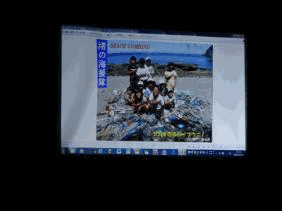
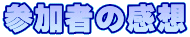 (講話を聞いて)
(講話を聞いて)