�@
���@�n���K�͂ł̊����
�����́A�S�l�ނɉۂ���ꂽ���ʂ̉ۑ�ł��B�l�ނ̗��j���n�܂����Ƃ�������Ƃ̖��ɒ��ʂ��Ă��܂��B�̉h���������̈�Ղ������ɂ悭����܂��B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ��h����ƔR���Ƃ��Ă̖���������K�v�ɂȂ�A�Ƃ�D����邽�߂ɂ�������̖��K�v�ɂȂ�܂��B�̖̂Ƃ����̂́A���̐Ζ��̂悤�Ȃ��̂ŁA�R���ɂ����ނɂ��Ȃ���̂ł����B�̂������Ă��܂��ƁA�����ς���Ă����ɏZ�߂Ȃ��Ȃ�A�������łтĂ��܂��Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B
���j�Ƌ��ɁA���������낢��ƕς���Ă��܂����B���x��������ɂ́A�u�����a�v��u�C�^�C�C�^�C�a�v�A�u�l���s�����v�Ȃǂ̌��Q��肪�������܂����B���̂���̌��Q���́A�ǂ��炪��Q�҂����Q�҂��A���ʊW���͂�����Ƃ��Ă��܂����A�����ꏊ���A��̌����Ă��܂����B���������̔r�o��}�����邱�Ƃɂ���āA��r�I�ɒZ���Ԃʼn������邱�Ƃ��ł��܂����B�������A���̒n�������́A�l�ޑS�̂������������N�����Ă���A�l�Ԃ��������邱�Ǝ��̂������̌����ɂȂ��Ă��āA���Q�҂Ɣ�Q�҂���ʂ��邱�Ƃ�����ł��B�܂��A�e���͈̔͂��n���S�̂ɋy��ł���̂ŁA����������Ȃ��Ă��܂��B�������̂��߂ɂ́A���C�t�X�^�C���̓]���ȂǁA���E�S�̂ō��ӂ��đΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Z���Ԃł͂Ȃ��A�����Ԃɂ킽���ĉ����̂��߂̑Ή������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�n���K�͂ł̊����́A�G�l���M�[�̑�ʏ�������̈�ƂȂ��Ă��܂��B�l�ނ��ǂ̂悤�ɃG�l���M�[���g���Ă����������Ă݂�ƁA�n�߂͉��g�������������̂ł����A�����ɂȂ�ƁA�ƒ{�ƕ��ԁA���ԂȂǂ̎��R�G�l���M�[���g���n�߂܂����B18���I�ɂȂ�ƁA���b�g�����C�@�ւ����ĐΒY���g���悤�ɂȂ�A�G�l���M�[���ʂɎg���悤�ɂȂ�܂����B����E���̂���ɂ́A�Ζ����g���n�߂āA�}���Ɏg�p�ʂ������܂����B���E�̈ꎟ�G�l���M�[����ʂ����Ă݂�ƁA����40�N�ԂŖ�R�{�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�X���قǂ��Ζ��A�ΒY�A�V�R�K�X�Ȃǂ̉��ΔR���ł��B���ΔR���͔R�₷���ƂŃG�l���M�[�����o���܂��B���̌��ʁA��_���Y�f�A�����������Ȃǂ̋C�̂�r�o���܂��B�F�������̒n���̗l�q�̎ʐ^���B�������̂����Ă݂�ƁA�d�C����������g���Ă���Ƃ��낪�����P���Ă��܂��B��Ԕ����P���Ă���k�āA�����[���b�p�A���{�ŁA���E�̐l���̖�20���̐l�X���A���E�̃G�l���M�[��60�p�[�Z���g���g�p���Ă��܂��B���̈���ŁA���ł���16���l���̐l�́A�d�C�̂Ȃ����������Ă��܂��B
���E�̐l���\���ł́A2050�N�ɂ́A�S�l����91���l�A���݂�1.5�{�ɂȂ�Ɨ\������Ă��܂��B�l�X���������Ă����̂ɂ́A�G�l���M�[���K�v�Ȃ̂ŁA�l����������ɂ��������ăG�l���M�[�̎g�p�ʂ������܂��B���E�̒��ł́A��i���̐l���͂��܂葝���܂��A�A�W�A��A�t���J�n��𒆐S�Ƃ������W�r�㍑�ł́A�l���������I�ɑ�������\�z�ł��B��l������̂f�c�o�ƃG�l���M�[����ʂ̊W�����Ă݂�ƁA�o�ς����W����قǃG�l���M�[�̏���ʂ�������X���ɂ���܂��B�t�ɍl����A�G�l���M�[����������g�����Ƃ��ł����������W���Ă����Ƃ������邩������܂���B�Ζ��Ȃlj��ΔR�������CO2�̔r�o�ʂƑ�C����CO2�Z�x�̕ω��̃O���t������ƁA�ǂ�����Y�Ɗv����ɐL�сA���ɑ��������E���Ȍ�}���ɑ������Ă��܂��B���ݓ��{�́A���E�̓�_���Y�f�̔r�o�ʂ̓��̂S����r�o���Ă��܂��B�����Ƃ���ł́A�A�����J��20���A������21���ł��B����2050�N����ɂ́A��_���Y�f�r�o�ʂ͌��݂̂Q�{�������ɂȂ�Ɨ\�z����Ă��܂��B
���̂悤�ɎЉ�̔��W�ɔ����ĉ��ΔR���𑽂��g���ƁA��_���Y�f�◰���_�����A���f�_�����Ȃǂ������r�o����A�n�����g����_���J�Ȃǂ̌����ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�t�����ɂ��I�]���w�̔j���M�щJ�т̌����ȂNJ��ւ̐[���ȉe�����o�Ă��Ă��܂��B���E�̖��N�̕��ϋC�������Ă݂�ƁA����30�N�ł��Ȃ�㏸���Ă��܂��B���{�ł������X���ŁA�Ăɂ͖ҏ����������A�~�ɂ͓~�����������Ă��܂��B��ɂ�k�ɂ̕X�������A�������Ȃ��Ă���ʐ^�Ȃǂ��悭������Ǝv���܂��B�k�ɂʼn��g�����i�ނƁA���E�̊C�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ɨ\�z����w�҂����܂��B�k�ɂŊC������₳��A�X���ł��邱�Ƃɂ���Ė��x���オ��A�d���Ȃ��Ē��݂���ł����̂��A�C���̌����Ƃ����̂ł��B�C�̐��͔M��~���鐫��������A�C���ɂ���Ċ����Ƃ���ɉ����������^��A�g�����Ƃ���ɗ₽�������^��āA�n�������g�ɕۂ���Ă���A�ł��A�C�����Ȃ��Ȃ�Ɗ����Ƃ���͂܂��܂������A�����Ƃ���͂܂��܂������Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����������܂��B�q�}������[���b�p�A���v�X�Ȃǂ̕X�͂��������Ȃ��Ă��܂��B��m�̏����ȓ��X�́A�C�����Ⴍ�A�C�ʏ㏸�ɂ���Ē��މ\�����w�E����Ă��܂��B�܂��A�C���㏸�ɂ���āA�`���a���L����Ƃ������Ă��܂��B���Ƃ��A�q�g�X�W�V�}�J(���u��)�́A�������N�Ő����悪�k�サ�Ă��܂��B���g�����i�߂A���{�ł��M�тɏZ��ł���}�����A��f���ʃ��O�M�Ƃ������`���a��}����̐�����ɂȂ�\��������܂��B
�_�Ƃւ̉e��������܂��B�A���ɂƂ��āA��_���Y�f��������̂́A�����𑣂��Ƃ����悢�_������܂����A�C��ϓ��ɔ����āA�i���̒ቺ���N����Ƃ������Ă��܂��B��B�ł́A�Ă̕i��������������A�݂���̓��Ă����N�������肵���ƕ���Ă��܂��B���Q���ł��A�݂���̔炪�����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��N�����Ă��܂��B�����Ă̎��n�ʂ��ǂ��Ȃ邩�\�z�����}������ƁA50�N��ɂ́A�k���{�ł͑������܂����A�����{�ł͂�⌸���X���A��100�N��ɂ́A������l���n���ł́A��������Ƃ��낪�����Ȃ�܂��B�܂��A�C�����R�x�㏸�����ꍇ�A50�N��ɂ́A�݂����������݂͔̍|�n���k�Ɉڂ�A���Q�ł��݂���͈�Ăɂ����Ȃ�ƌ����Ă��܂��B�����Ȃ�ƍ���̂ŁA��_���Y�f�����炻���Ƃ�������������̂ł����A�_�Ƃ�ыƂł́A�ނ���A���x�̕ω��ɍ��킹�Ĉ�Ă���̂�ς��Ă������Ƃ����l�����N�����Ă���悤�ł��B
�_���J�́A���ΔR���̎g�p�Ɩ��ڂɊW���Ă��܂��B��i���ł́A�ݔ��������Ă��āA�����ƂȂ钂�f�_�����◰���_��������菜�����悤�ɂȂ��Ă����̂ŁA�r�o�ʂ����X�Ɍ������Ă��Ă��܂��B�������A���W�r�㍑�ł́A�ݔ����܂�����Ȃ��̂łȂ��Ȃ����P���܂���B���{�Ō������Ă��O�����畗�ɏ���ĉ^��Ă������f�_�����◰���_�����ɂ���ē��{�ɂ���͂�_���J�͍~��܂��B�嗝��R���N���[�g�A�����Ȃǂ��n������A�X�̖��͂��Ȃǂ̔�Q���o�Ă��܂��B
����������Ƃ���ōX�ɍ������L����X��������܂��B���q�œ������A����H�ׂ�������A�d�Ȃǂ̔R���ɂ��邽�߂ɔ��̂��i��ł��邽�߂ł��B�܂��A�M�щJ�т̏Ĕ��_�Ƃɂ��A�X���������Ă��܂��B��@���̂�Ĕ��T�C�N���̒Z�k�ɂ����̂ł��B�܂��A�쐶�����̐�Ŋ뜜�킪�������Ă��邱�Ƃ����O����Ă��܂��B
�@
���@�n�������ւ̎��g��
�n�������́A����̒n��A����̗v���ŋN�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���낢��ȗv�������G�ɗ��ݍ����ċN�����Ă��܂��B���݊����ł́A�u�R�̂d�̃g�������}�v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B���݂̊����́A�G�l���M�[�̏���邢�͋�����A�o�ϐ����Ɛ[����������Ă��āA�o�ϐ���(Economy)�A�����E�G�l���M�[�̊m�ہiEnergy�j�A���ۑS�iEnvironment�j�A���̂R�̂d�������ɐ��藧���@��������Ȃ��Ƃ����Y�݂�����Ă��܂��B
�n���K�͂ŋN�����Ă�����ɁA���ۓI�Ȏ��g�݂��N�����Ă��܂��B1972�N�ɍ��A�l�Ԋ���c���s���A���̌�n���T�~�b�g�ŋC��ϓ��g�g���Ȃǂ����ꍡ���Ɏ����Ă��܂��B
�P�X�X�V�N�Ɂu�C��ϓ��g�g���@��R�����c�i�ʏ�COP3�j�v�����s�ŊJ�Â��ꂽ�Ƃ��A�u���s�c�菑�v���̑�����܂����B�������ʃK�X�̔r�o�ʂ�2008�N����2012�N�܂ł̂T�N�ԕ��ςŁA1990�N�Ɣ�ׂē��{�͂U���A�d�t�͂W�����炷���Ƃ����܂�܂������A�o�ςɗ^����e���������ăA�����J�͓r���Ŕ����܂������A���Ƃ��Ɣ��W�r�㍑�͓����Ă��܂���ł����B���{�̓I�C���V���b�N�ȍ~�A�ȃG�l�Ɏ��g��ł����̂ŁA�X�Ȃ�ȃG�l�Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ����������̂�����܂��B���EU�́A�������[���b�p���̒x��Ă����ݔ������P���邱�ƂŁA��̖ڕW��B�����邱�Ƃ��ł���ƌ����Ă��܂��B
���s�c�菑�ȍ~�̏������߂悤�Ƃ��Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ����܂�܂���B�܂��A���ɉ������Ă��鍑�œ�_���Y�f�r�o�팸�`�����Ă���̂́A�S�̂̂�����28���ɉ߂��Ȃ��̂ŁA���̍�������������Ă����̍����o������Ȃ�S�̂ł̍팸�͓���Ƃ���ł��B���̍��X�����͂��Č��炵�Ă����g�g�݂���낤��COP15��COP16�Ȃǂ��J�Â���܂������A�Ȃ��Ȃ����ӂ���Ă��܂���B���{�́A���̌�A2020�N�̔r�o�ʂ�1990�N���25���팸����Ɛ錾���܂����B�팸�ڕW��B�����邽�߂ɒlj��I�ɓ�_���Y�f1�g�����팸����̂ɕK�v�ȃR�X�g�́A���܂ł��Ȃ�̏ȃG�l�₢�낢��Ȑݔ������Ȃǂ����Ă������{�ł�476�h����������܂����A�A�����J�ł�76�h���AEU�ł�135�h���A�����ł͂킸���ȋ��z�ŒB���ł���Ǝ��Z����Ă��܂��B
���Ȃ��o�������Z�ɂ��ƁACO2��25�����炷���߂ɁA���X�̕�炵�̒��ł́A���ꂩ��V�z����Ƃ͂��ׂč��f�M�Z��ɂ��A�G�R�L���[�g�̂悤�ȍ�������������T���т̂����S���тɂ���A���z�����d�͂T���т̂����P���тɁA�n�C�u���b�h�J�[��d�C�����ԂȂǂ́A�V�Ԕ̔��̂���74���ɂ���Ȃǂ̂��Ƃ��K�v�Ƃ���Ă��܂��B�܂��A�G�l���M�[�����̖ʂł́A���z�����d�͌��݂�85�{�ɁA���͔��d��10�{�ɁA�������͔��d��15�{�ɑ��₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B���q�͔��d�ɂ��Ă�64��ɑ��₷�K�v������̂ł����A����͓���Ȃ��Ă��܂��B�����̂��߂̒lj��̓����z�͍ő�S���~���炢������ƌ����Ă��܂��B
�e�ƒ�̕��S���l����ƁA���f�M�Z��ɂ��邽�߂�100���~�A������������ł́A�q�[�g�|���v�ł���50���~�A�R���d�r�ł���100���~�A�Z��z�����d�ł́A230���~�A�����㎩���ԍw����40���~�`400���~�قǂ�����Ƃ����C���[�W�ł��B
CO225���팸�ɂ��o�ϓI�ȉe���ɂ��ẮA���ƌo�ς̗��������z�ł����A���{�����ł�����s�����ꍇ�A��������������4.5�`15.9���������A�}�C�i�X�̉e�����o��ƌo�ώY�ƏȂł͎��Z���Ă��܂��B
���ۂ�CO2�r�o�ʂ��݂�ƁA2008�N�x�́A��N��{1.6���Ɏ��܂�A�X�ыz������⋞�s���J�j�Y���ɂ��팸�����Ă���ƑO�N��|1.9���ɂȂ��Ă��܂��B2009�N�x�́A�X�ыz������⋞�s���J�j�Y���ɂ��팸�������Ă���N��|4.1���A�������܂߂�Ɓ|7.8���ɂ��Ȃ�A�����s�\���Ǝv��ꂽCO2�U���팸�����ۂɂ͂ł����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����������́A2008�N�ɂ��������[�}���V���b�N�������ŁA�o�ϑS�̂��k���������ʋN�������Ƃ����܂��B���܂芽�}���ׂ����Ƃł͂���܂���B2010�N�͂قڕς��Ȃ��ł��傤���A2011�N�ɑ傫�ȍЊQ�Ɍ������܂����B ���q�͔��d������~���A����ɉΗ͔��d�����ғ������Ă��܂��B100��kW���炢�̌��q�͔��d���P��ŁA�Ζ����g�������d���ւ���Ɠ��{�S�̂�CO2�r�o�ʂ��0.5���팸������ʂ�����܂��B�t�Ɍ��q�͔��d���Η͔��d�ŕ₤�ƂȂ�ƁACO2�r�o�ʂ͑����Ă����܂��B�܂��A�ЊQ�̉e���Ōo�ς���ނ���A����Ȃɑ����Ȃ���������܂���B�܂��A�\�������Ȃ��Ƃ���ł��B
���́A���d�̒�Y�f���ɂ��Ăł��B���{��CO2�r�o�ʂ̖�R�����Η͔��d���ŏo���Ă��܂��̂ŁA���d�̒�Y�f�����l���邱�Ƃ͑傫�ȈӖ�������܂��B�d���ʂɌ���ƁA���CO2�r�o�ʂ������̂͐ΒY�Η͂ŁA�k�m�f�ł́A�ΒY���͏��Ȃ��Ȃ�A3����2�قǂɂȂ�܂��B���z���A���́A���q�͔��d�Ȃǂ́ACO2��r�o���܂���B�n�k�ȍ~�k�m�f���g�����ƌ����Ă��܂����A�ΒY���k�m�f�ɒu���������CO2������܂����A���q�͂��k�m�f�ɒu���������̂ł́ACO2�͂������đ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B��v���̓d���ʔ��d�d�͗ʂ����Ă݂�ƁA���{�͐ΒY�E�V�R�K�X�E���q�͂����ꂼ��25�����قǂŁA�o�����X���Ƃꂽ�\���ɂȂ��Ă��܂��B�ǂꂩ������߂ɂȂ��Ă����ŕ₦��悤�ɂ��Ă���̂ł��B����ɑ��A������C���h�͐ΒY�������A�t�����X�͌��q�͂��W���قǂ��߂Ă��܂��B���̂悤�ɍ��̍l�������d���̊����ɏo�Ă��܂��B
���{�̔��d�d�͗ʂ�25���قǂ��߂Ă��錴�q�͔��d�̌���ł����A13�����ɂP�x����_�������邱�Ƃ����܂��Ă��܂��B���{�̓d�͎��v�̃s�[�N�͉ĂȂ̂ŁA�t�ƏH�ɍs���邱�Ƃ������ł��B���݂́A�k�Ђ̉e���Œ���_�����I����Ă��ċN���ł��Ȃ����̗��R��54��̓���38���~���Ă��܂��B��25���̓d�͋����ʂ̂V�����g���Ȃ��ł��B�������Ă��锭�d�����A������_���ɓ���A�_�����I����Ă����������邩������܂���B�ɕ����d���ł́A���݂R����~�܂��Ă��āA�X���ɂ́A�P�������_���ɓ���܂��B���N�̂P���ɂQ�������_���ɓ���ƁA���ׂĂ��~�܂�܂��B�l���̓d�͂̂S�����������Ă����̂ŁA�������̕��������o���Ă����Ȃ��ƁA��������ԂɂȂ�Ǝv���܂��B
���[���b�p�̏ꍇ�A�������ł�����d�̗͂A�o�����\�ł��B�h�C�c�ł́A�E���q�͔��d��錾���܂������A����Ȃ��d�͂��A�W�������q�͔��d�ŋ������Ă�����̃t�����X���甃�����Ƃ��ł��܂��B�K�X�̃p�C�v���C���Ԃ��L�����Ă��āA�G�l���M�[�Ɋւ��āA���[���b�p�͒n��S�̂ōl���邱�Ƃ��ł��܂��B���{�̏ꍇ�A����͊C������܂����A�߂��̍��X�Ƃ̊W�̖ʂł�������̂�����܂��B
�l���d�͂̍�o���d���ł́ACO2�r�o�����炻���ƁA�R�����d����ΒY����k�m�f�ɓ]�����Ă��܂��B
�܂��A���d��������̔r�C����CO2���W�߂Ēn���ɒ������悤�Ƃ������݂��s���Ă��܂��B�������A��_���Y�f�����k����̂ɔ��d�����d�C�G�l���M�[��30���قǂ��g��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ȂǁA�܂������J���i�K�̋Z�p�ł��B
�V�G�l���M�[�A���z�����d�╗�͔��d�́A�������͊�����S�z�̂Ȃ��N���[���ȃG�l���M�[�ł����A�V�C�ɂ���Ĕ��d�ł��Ȃ��Ƃ����f�����b�g������܂��B���z�����d�́A��Ԃ͔��d�ł��܂��A���d�R�X�g��49�~/kWh�ŁA�ƂĂ������ł��B�ɕ����q�͔��d���͂P�`�R����ŁA��200��kWh�قǏo�͂�����܂����A����ɑ�ւ��悤�Ƃ���ƁA���z�����d�ł́A�����l�s�قǂ̖ʐςɑ��z�d�r�p�l������ׂ�K�v������܂��B���͔��d�ł́A���Ԃ��V�`�W��{���Ă�K�v������܂��B���R�s�قǂ̖ʐς��K�v�ŁA�������������̐����Ƃ���Ɍ��Ă�K�v������܂��B����𒆐S�ɔ��d��i�߂Ă����̂́A��������Ƃ��낪����܂��B�����Ƀ��K�\�[���[�A���R���z�����d�������Ă��܂����B���K�\�[���[�Ƃ͌����܂����A�Η͔��d�����Ɣ�r����ƁA�o�͂͂܂��܂��͏��������̂ł��B�܂��A�V�C�ɂ���ďo�͂��ϓ����܂��B���V�̎��͂����̂ł����A�܂����Ƃ��A�J���~�����Ƃ��ɂ́A���d�ł��܂���B�o�͂����肵�Ȃ��̂ŁA�����₤���߂̕ʂ̔��d����ҋ@�����Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B���R���z�����d���Ŏg���Ă��鑾�z�d�r�p�l���́A�P��������ő�o�͂�193W�ł��B������̗�ł����A���V�̂Ƃ��A126W���d���Ă���ꍇ�ł��A�����l�̉e���������20W�قǂɉ������Ă��܂��܂��B�ꕔ�����S�ɉe�ɂȂ�ƁA�UW�ɂ܂ʼn������Ă��܂��܂��B���{�̂��ׂĂ̏Z��̉����ɑ��z���d�r�p�l�������悤�Ƃ����b������܂����A�r���̉e�ɂȂ����Ƃ�A�����������E�k�����̉Ƃł͔��d�͓���A�Ⴊ�ς���Ƃ���ł͂���ɓ�����ł��B
���͔��d�́A�l���S�̂�102��A���̓����c����58���܂��B���̂����Ƃ���Ɍ��ĂĂ��܂����A���d�͕����ʂ蕗�C���ł��B
�؎��o�C�I�}�X���d�ɂ��ẮA�ޗ��ƂȂ�؍ނ�����I�ɋ����ł��Ȃ��Ƃ�����_������܂��B�܂��A�����͔��d�́A�_�������Ȃ��Ă��삪����Ă���Ƃ���ɐ��Ԃ�������̂ŁA���܂�傫�Ȃ��̂͂����܂��A���̑���V��ɂ����E���ꂸ�A����I�ɂ����܂��B�������������̖����������Ȃ��Ă͂����܂���B�n�M���d�́A�ꏊ������n�⍑���������ɂ��邱�Ƃ������A�����͂����Ă����p�͂��ɂ����ł��B�g�͔��d�A�������d�Ȃǂ�����܂����A�����i�K�ł��B
���낢��ȋZ�p��p���āA�����Đ��\�G�l���M�[���̂��낢��Ȕ��d��������ʂɓ����ł���悤�ȓd�̓l�b�g���[�N���\�z���A�ȃG�l��������ɂȂ��Ă������Ƃ����l�������X�}�[�g�O���b�h�ŁA���ꂩ�瓱�������߂��Ă��܂��B
�H��ł̏ȃG�l���M�[���̂��߂ɁA�ȃG�l�@������܂����B�������Z��1500kw�ȏ�g���Ă��鎖�Ǝ҂́A���N�ǂ̂��炢�G�l���M�[���g���Ă��邩���ׁA�G�l���M�[�Ǘ�������l����u���A�������I�Ɍ��ĔN���ςP���ȏ�̃G�l���M�[��������炵�܂��傤�Ƃ������Ƃ��`���Â����Ă��܂��B����20�N�ɉ�������āA���̎��Ə��P�ʂőΏۂƂȂ�̂łȂ��A���ƎҒP�ʂőΏۂɂȂ�܂����B�܂�A�R���r�j�G���X�X�g�A��t�@�~���[���X�g�����Ȃǂ̃`�F�[���X���A���͏���������ǏW�܂�Α傫���Ƃ������ƂŏȃG�l�@�̑ΏۂɂȂ�܂��B���l�ɁA�����̂��A�{���r�������łȂ��A�����w�Z������فA�X���Ȃǂ��܂܂��̂őΏۂɂȂ�܂��B�ߔN�̃G�l���M�[�̎g�����ł́A�Y�ƕ�����A�����E�^�A����ł̐L�т��傫���Ȃ��Ă������߂ł��B�N���ςP���̍팸�͏��߂͐ߖ�ŒB���ł��Ă��A����ߖ��ł͍ς܂Ȃ��Ȃ�A�V�������̂ɐݔ���ւ���Ȃǂ̂��Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@��̌������ł��A�g�b�v�����i�[����݂����A�����Ԃ̔R���G�A�R���A�①�ɂȂǂ̓d�C�@��̐V�������i�̏ȃG�l���M�[������ݏ��i������Ă��鐻�i�̂����A�ł��D��Ă���@��̐��\�ȏ�ɂ���悤�Ɍ��߂��Ă��܂��B�G�A�R����①�ɂł́A�����傫���ł�10�N�O���50���ȃG�l�ɂȂ��Ă��܂��B�e���r�ł́A�R���̂P�قǂɂȂ��Ă��܂��B
�Y�ƕ�����A�����E�^�A����ł̐L�т��傫���ł��B�Z�p�v�V�ɂ���ċ@��̃G�l���M�[�g�p�ʂ͌����Ă���̂ɁA�Ȃ��ꐢ�т�����̓d�͎g�p�ʂ͑������Ă���̂ł��傤�B�ƒ�ł̓�_���Y�f�r�o�ʂ�����ƁA�d�C���炪42���قǁA�K�\�������炪30���قǂɂȂ��Ă��܂��B���ꂼ��̋@��̏ȃG�l���M�[�����i��ł���̂ł����A�e�ƒ�ł̉Ɠd���i�̐��������Ă���̂ŁA���ʓI�ɓd�͎g�p�ʂ������Ă���̂ł��B�e�����ɃG�A�R�����t���Ă�����A�e���r�̑䐔�������Ȃ�����A�①�ɂ��傫���Ȃ����肵�����߂ł��B
�q�ǂ������ɃG�l���M�[�̘b������Ƃ��A�d�C�@���K�X�̂悤�ȖڂɌ�����G�l���M�[�����ł͂Ȃ��A�ԐړI�ȃG�l���M�[�ɂ��Ă��b�����Ƃ�����܂��B�ԐڃG�l���M�[�Ƃ́A���낢��Ȃ��̂Y������A�^�肷��Ƃ��Ɏg���Ă���G�l���M�[�ł��B���Ƃ��A�Ă���ĂāA���n���A�o�ׂ���̂ɕĂP�s������0.35���b�g���̌������g���Ă���v�Z�ł��B�m�����ƁA�P��������V���b�g���ł��B�����āA����ď������A�p������Ƃ���܂ł��l����ƁA�ƒ�Ȃǂœd�C��K�X�̂悤�Ȓ��ږڂɌ�����G�l���M�[�Ɠ������A��葽���ƌ����Ă��܂��B
��͔̍|�ɂ�����G�l���M�[��I�n�͔|�ƃn�E�X�͔|�Ŕ�ׂĂ݂�ƁA�L���E���ł́A8.1�{�A�g�}�g�ł́A9.7�{���n�E�X�͔|�ɃG�l���M�[���g���܂��B�P�����̃L���E������邽�߂ɁA�I�n�͔|�ŏ{�̎����ɐ��Y����ƁA�����G�l���M�[�ʂ́A996kcal�ł����A�n�E�X�͔|�ł́A5054kcal��������A���̂قƂ�ǂ����M��ł��B�����ō͔|���邾���łȂ��A�C�O����H�Ƃ�A�����Ă���̂ŁA���̗A������ł���ʂɃG�l���M�[������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����������ƂɁA�ǂꂮ�炢��_���Y�f���������Ă���̂���ڂɌ�����`�ɂ��悤�Ƃ������ƂŁA�u�J�[�{���t�b�g�v�����g�v�Ƃ������x�����s����Ă��܂��B���̐��i�̌����̒��B����p���܂łɂǂꂾ���̓�_���Y�f���r�o����邩���A�H�i�\���ȂǂƓ��l�ɋ`���t���悤�Ƃ����������o�Ă��Ă��܂��B�t�����X��C�M���X�ł́A���i�Ȃǂ̎c������_���Y�f�̑��ՂƂ������ƂŁA�}�[�N�����Ռ^�̂��̂ɂȂ��Ă��܂��B���{�ł́A�܂������i�K�ł����A���{�n����C�I���A���{�H���Ȃǂ��Q�����Ă��܂��B
�@
���@�I���Ɂ@
�G�l���M�[�����̂��ꂩ��̉̔N���́A�Ζ�42�N�A�V�R�K�X60�N�A�ΒY122�N�A�E����100�N�ƌ����Ă��܂�������͂Ȃ��Ȃ邱���̎����ȊO�ɁA���^���n�C�h���[�h��I�C���T���h�A�I�C���V�F�[���Ƃ��������܂Ŏg���ɂ����������̂��g������A�o�C�I�}�X�G�l���M�[�ȂǁA�J�[�{���j���[�g�����ȃG�l���M�[�̗��p�����҂���Ă��܂��B
����Ɗ��������Ȃ�B���ۑS�ɗ͂������ƁA�G�l���M�[�͏���Ȃ����A�o�ϔ��W���}������Ƃ����悤�ɁA�u�R�̂d�̃g�������}�v�̂ǂ̂�����Ő܂荇����t���邩����Ƃ���Ō��_���ȒP�ɏo�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����A����̍u���͂���ŏI���ɂ��܂��B���������肪�Ƃ��������܂����B
�@
�@
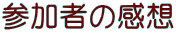 �i�u�b���āj
�i�u�b���āj
�E�n�����g���A�I�]���w�̔j��A�_���J�A�������̐i�W�A�M�щJ�т̌����A�쐶�����̌����@�ȂǁA�n���K�͂ł̊����͂��܂��܂ȂȂ���̒��ň����N�����Ă��邱�Ƃ��������@���B�n�������̉����Ɍ����āA�����������łł��邱�Ƃ����悤�Ƃ����C�����ɂȂ��@���B
�E�n�����g���ɂ��l�X�ȉe�����悭���������B�����̒n������邽�߂ɁA�q�ǂ������ƂŁ@���邱�Ƃ�����g��ł��������Ǝv���B
�E�l�X�Ȕ��d���@��ŐV�̋Z�p�Ȃǂ�m��A�܂��A�q�ǂ������Ƃ����낢��ƒ��ׂĂ������@���Ǝv�����B
�E�G�l���M�[�Ɛl�ނ̗��j����ŐV�̃G�l���M�[����܂ŁA�����̎����������ɍu�b�������@���A��������G�l���M�[���ɂ��ĊS�����߂邱�Ƃ��ł����B
�E�n���K�͂ŋN�����Ă�������ɂ��ĉ��߂ĔF���ł����B��������낢��ƒ��ڂ���@�镪��Ȃ̂Ŏq�ǂ������ɂ��p�����Ďw�����Ă��������B
�E���݂̃G�l���M�[�̏ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł����B�g�������}�Ƃ������t���S�Ɏc�����B�@�o�ρE�G�l���M�[�E���ۑS�̃o�����X���ǂ�����Ă��������l���Ă����Ȃ���Ȃ�ȁ@���Ǝv�����B�����ɂł��邱�Ƃ��ꐶ�������g��ł���q�ǂ������̓w�͂����ʂɂȂ�@�Ȃ��悤�ɂ������B
�E�����̒��̗l�X�ȏ�ʂŃG�l���M�[���g���Ă��邱�ƁA�܂����̃G�l���M�[�̎g�p�����@�����邽�߂ɗl�X�Ȗ@�������邱�Ƃ����������B
�E��������̎��������Ƃɐ��I�ɃG�l���M�[�ɂ��ču�b���Ă��������A�m���Ƃ��Ēm��@�Ȃ��������Ƃ��͂����肵�����Ƃ����������B���q�͔��d�̑���ƂȂ锭�d������A�@���ꂩ��̓d�͂��s���ł���B
�E���g���ɂ��n���K�͂̊��ω��̗l�q���悭���������B�_�앨�A�X�́A�C�ʏ㏸�Ȃǂ́@�ω�����̓I�ɗ����ł����B�P�O�O�N�A�Q�O�O�N��̒n�������Ől�Ԃ⓮�����ǂ������@�Ă������S�z�ł���B��i���́A�d�C���Ȃ��Ă͐������ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B�����̌����@���̌�A���肵���d�͂̋������ł��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ɩ�莋����Ă���B�������A�d�͉�@�Ђ������̈��S�ȓ��{�̂��߂ɁA�ڐ�̗��v��ǂ킸�A�m�b���o���čl���Ăق����B
�E���{�̌���ɂ��Ă̕��͂ƁA�\���ɂ��Ẳ���������̂łƂĂ������[���������B���@�G�ő�ςȋǖʂɗ����Ă���Ɗ������B
�E�G�l���M�[�Ɗ����Ƃ́A�g�߂ȂƂ���ɂ���Ɖ��߂Ċ������B���ꂩ��̎�����@��q�ǂ��������ǂ���ĂĂ����悢�̂��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ������B
�E������邱�Ƃ̑���͓��ł͕������Ă�����̂́A���ۂɂ͖����̐�����D�悳���ā@���܂��Ă��鎩���ɍs�����������B���悢���Â���̂��߂ɁA�g�߂Ȃ��Ƃ��班�����@���g��ł��������B�܂��A���X�Ɛ[�������Ă�������ɂ��Ēm��Ȃ����Ƃ̕|�@�����������B�������łȂ����������߂Ȃ��������ɂ��čl���A���H���Ă������Ɓ@�̑�������߂Ċ������B
�E���̒n���̐l�ނ̕����Ă�����̐[�������悭���������B�����ɑ���G�l���M�[���Ɓ@���Ă̑��z�����d�ɂ����낢��Ȗ�肪����̂��ƕ��������B
�E���␢�E�K�͂ł̃G�l���M�[��������ɂ��Ă̘b�������ĎQ�l�ƂȂ����B
�E�G�l���M�[���͈꒩��[�ɉ����ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��悭���������B�������A�����@��Ƃ����ĉ������Ȃ��ł����Ă͒n���̊��͎��Ȃ��B��l��l���G�l���M�[��������@�炵�A�ł�����̂���V�G�l���M�[�ւƓ]�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ������B
�E�G�l���M�[�����邱�Ƃ̑�ς���ɐɊ������B���邢���������邱�Ƃ��ł���̂��@�s���ɂȂ����B�Ƃ肠���������łł���ߖ�𑱂��Ă������Ǝv���B
�E���l��O���t�ɂ��A���̕ω����͂�����ƕ��������B���Ƃ��Ă̎�g���K�v�����A�@�l�łł��邱�Ƃ���������Ǝv�����B
�E���̐����ŃG�l���M�[����ʂ��팸���邱�Ƃ͓���ƕ��������B���ꂾ���Ɉ�l��l�́@�n���Ȋ��������ʂ��グ��̂��Ǝv�����B
�E�n���K�͂ł̊���肪�A���ɐ[���ȏɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A��̓I�ɃO���t��ʐ^�@�Ő������Ă����������̂ŁA�悭���������B��l��l���ӎ����Đ�����ς��邵���Ȃ��́@���ȂƎv���B
�E���e�͓�����̂ł��������A�����}�Ȃǂ������ĕ�����₷�������Ă����������B
�E�ƂĂ�������₷�������B�H�Ǝ������ȏ�ɁA�G�l���M�[�������̐[�����ɂ��Ďq�ǂ��@��������[�߂�ׂ����Ǝv���B
�E������₷���Ă悩�����B�m�������߂邱�Ƃ��ł����B���Ƃ̎����Ƃ��Ă��g������̂��@�������B
�E���̃G�l���M�[�̌��悭���������B���q�͔��d�ɂ��ẮA���猻��ł͂ǂ̂悤�Ɂ@�q�ǂ������ɘb�������̂��Y�ށB
�E�G�l���M�[�ɂ��Ēm��Ȃ��������Ƃ������������̂łƂĂ����ɂȂ����B�G�l���M�[�@�Ɗ��Ƃ͖��ڂȊW�ł���A���������ɂ́A�o�ρE���ۓI�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@�Ǝv�����B
�Eeco�Љ�Ɍ����Ă̎������̎�g�́A�l�Ԃ̕����Љ�S�̂̈ꕔ�������͉ƒ�̎�g�����@����Ȃ����A��l��l�̈ӎ��ɂ���Ďx�����Ă������̂ł��邱�Ƃ����������B
�E�G�l���M�[�̐��Y�R�X�g���l����Ɖ����ł��Ȃ��悤�Ɏv���B�ƒ���ł́A�G�A�R���ƃe�@���r�̎g�������B
�E�b�n�Q�̍팸�A�ȃG�l�ɂƂĂ�������������ƕ����ċ������B������邱�ƁA�悭����@���Ƃ͑�ςȂȂƎv�����B
�E��������Ă������߂ɁA���낢��Ȍ���������Ă��邱�Ƃ��悭���������B�����̂��Ɓ@�Ƃ��čl���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�E�G�l���M�[�Ɗ��ɂ��Ď���������������Ă��������āA������Ƃ�����Ȃ��@�Ƃ������Ă������������ƂɊ��ӂ���B���E���x���ŁA�������X�s�[�h�ŕς���Ă����@���ɂ��ĐV���������A��X�͂ǂ�ǂ���肵�������Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B�@���E���w�Z�̋���ɊW���邱�Ƃ�������������悩�����B
�E���ꂩ��̐����͂ǂ��Ȃ�̂��낤�ƕs���ɂȂ��Ă��܂����B
�E�ƂĂ�������₷���������������Ă���A����Ɋ�Â��b�������̂ŁA�G�l���M�[�Ɗ��@�ɂ��Ă̊�@�����������B
�E���i�Ȃ��Ȃ��������Ƃ̂Ȃ��A�G�l���M�[�̗l�X�Ȃ��b�����Ă��������A��ϋ����[�@�������B
�E���{�̃G�l���M�[����悭���������B
�E���L�������Ă����������B���������s���|�C���g�ŏڂ��������Ă��������̂������B
�E�܂��܂��m��Ȃ����Ƃ��肾�����̂ő�ϕ��ɂȂ����B
�E�V�����G�l���M�[�ɂ��Ă⍡�̌���A��g���ƂĂ�������₷���������Ă��������ė��@�����邱�Ƃ��ł����B
�E���₷��������₷��������p���Ă���������ɂȂ����B
�E�L���m����^���Ă��������Ă��肪���������B
�E�����ʂɂ킽�鑽���̎���������������ɂȂ����B
�E�b�̂���܂��͂悭�����ł������A�u������v�̎��_�Ƃ��Ďq�ǂ��̗��ꂩ��ǂ����ā@���������l����������̂ɂ��Ăق����B���e�����������悤�Ȋ�������B
�E���nj��q�͔��d�̕K�v����i���Ă���悤�Ɏv�����B�u���Ƃ��Ă͖�肪����̂ł́B



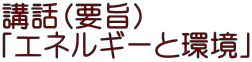
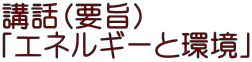
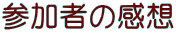 �i�u�b���āj
�i�u�b���āj