1 研究内容
新居浜市では、各学校で取り組んでいる環境教育について交流を深め、進んでよりよい環境づくりに取り組む児童生徒を育成するため、平成19年度より「にいはま子ども環境サミット」を開催している。
(1) 「にいはま子ども環境サミット」の概要
・ 平成19年度より開催されており、毎年7月下旬の夏季休業中に実施している。
・ 市内各小学校の代表児童数名と引率教師数名、保護者、及び一般の方々が参加。
・ 前半は、代表校が自校の環境保護の取組を発表し、それを中心に協議する。
・ 後半は、外部講師を招き、出前講座などで環境保護の大切さを学ぶ。
(2) 「にいはま子ども環境サミット」の内容
・ 参加児童による自己紹介や意見交換。
・ 体験活動の発表後、感想発表、及びアンケート。
(3) 市内各校の取組
|
|
| 学校 |
取組及び活動内容 |
宮西小学校
|
○ エコキャップ回収運動
・プリントやポスター作り。
・エコキャップ回収箱作り。
・放送による呼び掛け。
・エコキャップの集計、引き渡し。 |
新居浜小学校
|
○ 環境を守るために自分たちにできることを考えよう
・代表委員会での話合いをもとに、牛乳パックのリサイクルを行うことにした。 |
角野小学校
|
○ 身近なことで、自分のできることから始めよう
・朝のアルミ缶回収活動。
・エコ点検の実施。
・自然を大切にする活動。 |
神郷小学校
|
○ エコスクール活動
・エコ講座〜ゴーヤ栽培〜
・6年生からエコプレゼント。 |
新居浜東中学校
|
・資源回収。
・有志による、河川敷清掃。 |
川東中学校
|
・地球規模での地球問題について、また新居浜市の現在の生活環境について考える。
・新居浜市のゴミの実態調査をもとに、今後どうすればよいのか考える。
・家庭や学校で実際にできるリサイクルについて考える。
・家庭や学校で実際にできるエコ活動や省エネについて考える。
・川東校区や川東中学校の、さらなる緑化について考える。 |
新居浜西中学校
|
・グリーンカーテンの設置。
・エコ織物づくり。 |
|
2 成果と課題
○ 4年間の子ども環境サミットの実践で、先進校の取組を市内各校へと広げていくことができた。
○ 環境サミットに参加することを通して、児童の環境保護活動への意識が高まった。
○ 一般の方にも参加してもらったり、市政だより等で広報していただいたりすることで、各小学校の取組を市民の方々に知ってもらうことができた。
● 回数を重ねていくごとに、発表校の選定が難しくなっている。同じ学校が発表すると、取組を広めるという効果が薄れてしまう。
● 夏季休業中の開催のため、児童の事前・事後指導が難しい。また、会場への行き帰りを保護者に任せるため、参加できない児童もいる。
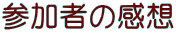 (新居浜市環境教育主任会の発表を聞いて)
(新居浜市環境教育主任会の発表を聞いて)
・ 本町にも、新居浜市の取組のような会議がある。その会に参加・参席するにあたり、環 境に目を向ける学校の取組や子どもの育成が図られているように思う。子どもたちを対象 として、町同士の交流的な部分ができると、一層の効果が上げられるのではないかと思う。
・ 環境サミット開催など、市をあげての取組はすばらしいと思う。小学生より環境につい て学ぶことは大切。
・ 市として、各学校とつながり、連携する中で、お互いのよいところを見習い、相互に学 習する環境が整っている。
・ にいはま子ども環境サミットを中核に、市内の子どもたちが集まり、交流しながらお互 いに刺激を受けて、ともに環境問題に取り組んでいった様子がよく分かった。自分の学校 だけでなく、他校にも仲間がいるという意識は、子どもたちの視野を広げるためにも大切 であろう。
・ 新居浜市全体で交流しながら環境教育に取り組む姿は立派であり、本町の研究推進に生 かしていきたい。特に環境サミットが興味深かった。
・ 各学校の交流の場である「にいはま子ども環境サミット」が組織化されているのがすご いことであると感じた。ぜひ、今後も続けてほしい取組である。
・ 新居浜市全体で環境教育の交流会を開くことによって児童相互に学び合うことができる のでとてもよい取組だと思った。他校の活動に刺激を受け、自分たちでエコについて話し 合うことが何よりの環境教育だと思う。
・ にいはま子ども環境サミットを通じて、子どもたちが交流を深め、情報交換をしていく 中で、環境保全に対しての共通理解が図られたと思う。また、各地域で取り組むべきこと や、課題を再認識することができたと思う。
・ 各校が単独で取り組むのではなく、市内の小中学校が交流をしながら環境教育を進めて いることに感心した。高校とも連携できると理想的だと思う。
・ 市内の各学校の横のつながりが教育の成果を高めていることがよく分かった。
・ 子どもの主体性を大切に、引き出す取組がなされていると思った。
・ 市内の小学校や中学校がそれぞれ活動したり、または連携して様々な活動をしたりする ことを通して子どもたち一人一人が意識を高めているのだと思った。環境教育での「小中 連携」はとても勉強になった。
・ 各校が自分たちのできる活動に取り組んでいることがすばらしい。イベント的ではなく、 継続できる活動なので、環境教育を継続させることができてすばらしい。
・ 市内で同様な取組をすることで相乗効果が生まれ、共通の課題に対しても改善できると 思う。
・ サミットという形式で交流し、情報交換や活動の発表の機会があることが、全市的に環 境に対する意識の高まりや活動の広がりにつながっていると思う。
・ 子どもたちから「環境サミットをしたい」と意見が出ていることがすばらしいと思った。 新居浜市の子どもたちが、よりよい環境づくりについて考えを深めることができているこ との表れではないかと思う。
・ 「環境サミット」開催の提案が、小学生からあったことがすばらしいと思った。児童・ 生徒が進んで環境について考え、自分でできること、他者に伝えたいことをまとめていく ことで将来につながっていくのだと思った。
・ 環境サミットは、大人が与えたものではなく、子どもたちの要望から上がってきたこと がすばらしい。だからこそ、様々な学校に波及している。一人一人の小さな取組が、多く の学校で同じ歩調で取り組むことにより大きなうねりとなる。それが環境教育の一番大切 な点だと思う。
・ 子どもサミットという取組が子どもたちからの提案で始まり、今年度も引き続き行われた点が特に興味深かった。また、各校の取組も多様報告していただき、今後の取組の参考となった。
・ エコサミットを通して、小学校段階から環境に対する意識付けができていると思った。 児童提案によりエコサミットが始まったことや市全体で交流をもっているところなどすば らしいと思った。
・ 生徒たちが主体となった取組があり、参考となった。
・ どこの学校でも自分たちに何ができるか考え、できることから始めていこうという取組がいいと思った。市全体で取り組むのがすばらしい。
・ どこの学校でも委員会を中心に取り組んでいることがよく分かった。自分たちにできることをみんなで行っているので、自分たちのためになる取組だと思った。
・ 環境サミットすばらしい。内容的には本校でも取り組んでいるものがいくつかあるが、まだまだ取り入れることができるものが多々あり、参考になった。
・ サミットの取組で、自校だけでなく他校、地域の取組を知り、広げていることがすばらしいと感じた。
・ 児童の思いから環境サミットが開かれるようになったことに驚きを感じた。市全体で環境教育に取り組んでいることがすばらしい。
・ 各校がそれぞれの実態に合わせた活動をされていて、すばらしいと思う。このような地道で細かい活動をどの学校でも行っていけばよいと思う。
・ 環境サミットをすることで、各学校の取組を知ることができ、よいところをまねできるメリットがあると思った。
・ 環境サミットを続けることは大変だと思う。工夫・改善を加えながらぜひ続けていってほしい。
・ 新居浜市と同じように「環境子ども会議」を年一回行っている。各校で取り組んできた内容を発表し合って意見交換を行っている。他校の取組を知ることにより、次の啓発にもつながっていると思う。
・ 環境サミットを通して、環境問題について考える実践はすばらしい。継続していくために変化のある取組の工夫が大切だと思う。
・ 市内のたくさんの学校で、各校ができる環境教育に取り組んでいるのがすばらしい。
・ 市内全体で結束して取り組んでおられてすばらしいと思った。自校でも取組に生かしたい。
・ たくさんの取組が紹介されていて参考になった。
・ 市内で環境サミットを実施し、それぞれの学校独自で環境に向けた取組ができていた。
・ 各小・中学校の取組を紹介してくれたので、簡単なものは自校で取り組んでいけるもの もあって参考になった。
・ 新居浜市内のいろいろな学校の取組がよく分かった。エコ織物は家庭科の授業でもでき るなと思った。
・ 新居浜市は、水泳大会、合唱コンクールなどの様々な活動がある7月の末に各校がエコサミットで取組を発表しているのはすばらしいと思う。
・ 地域の実態に合わせて、それぞれ工夫して活動できていた。
・ お祭りや花火大会後の清掃活動はすばらしいと思う。



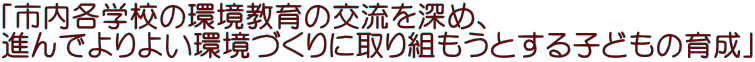
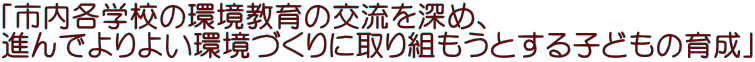
![]()